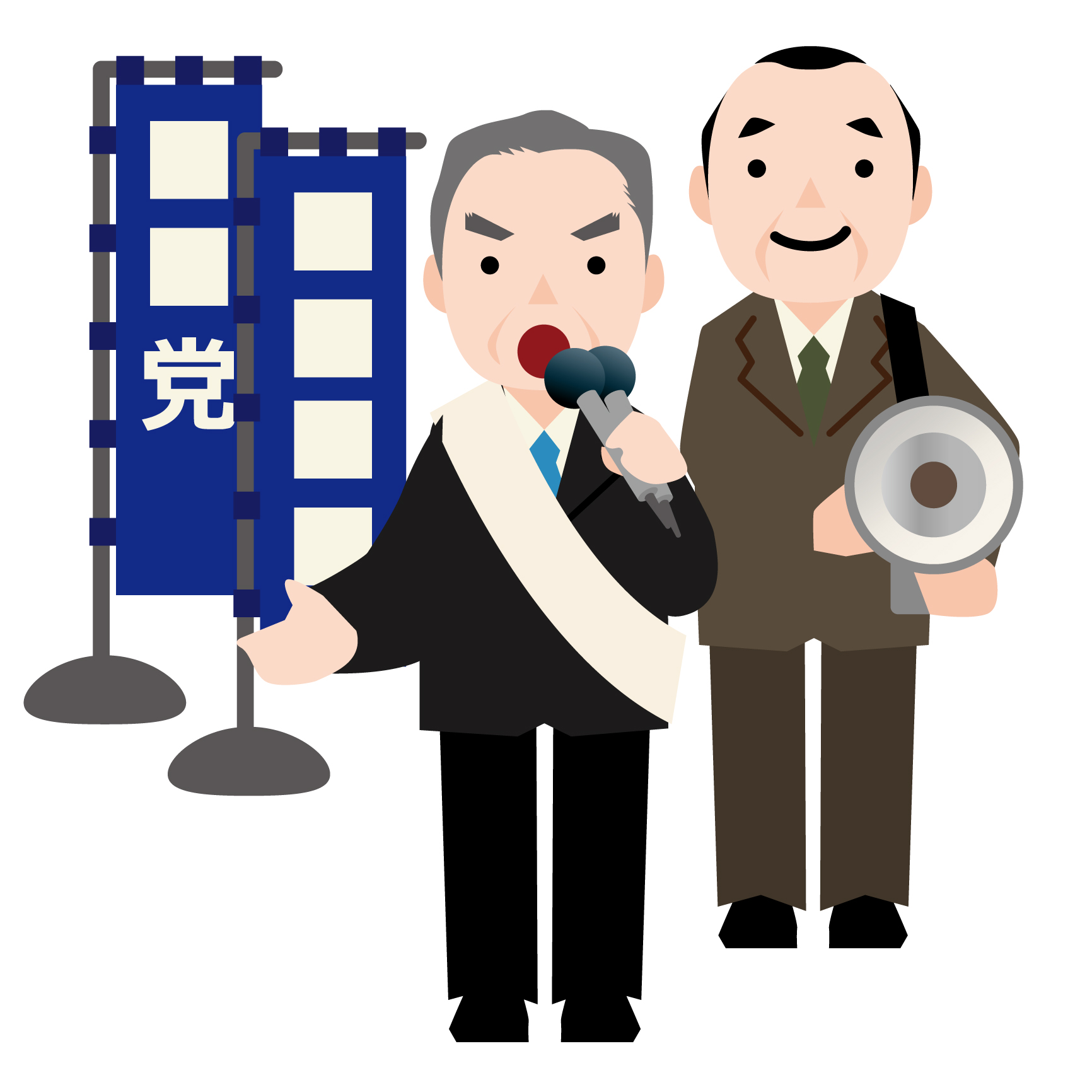表向きは「国民の代表」、でも本音は?
多くの政治家は、選挙のたびに「国民のために働きます」と口にします。街頭では笑顔で手を振り、政見放送では丁寧な言葉で政策を語ります。
けれど、当選後の言動を見ていると、「本当にこの人は私たちを信用しているのか?」と疑いたくなるような振る舞いが散見されます。
たとえば、議会での強行採決や、都合の悪い質問にはぐらかしばかりの答弁、説明責任を果たさない態度。これらは、まるで国民が政治に無知で、簡単にごまかせると思っているかのようです。
「どうせ国民は関心を持たない」「説明なんてしても伝わらない」—そんな空気が、一部の政治家の中に根深くあるのではないでしょうか。つまり、彼らは国民の知性と判断力を信用していないのです。
「無関心でいてくれた方が助かる」
さらに問題なのは、そうした政治家たちが、あえて国民の政治参加を妨げるような空気を醸成していることです。
政策を分かりにくくし、選挙制度を複雑にし、情報公開を後ろ向きにする。これらはすべて、国民が「めんどうだ」と思って政治から距離を置くように誘導するための“無言の戦略”です。
なぜそんなことをするのか? 答えは簡単です。政治に関心を持つ人が増え、投票率が上がると、自分たちが次の選挙で落選するリスクが高まるからです。
組織票や利害関係でガッチリ固めた選挙基盤に依存している議員にとっては、無党派層や若年層の票が増えることは“読みづらい”危険因子です。
だからこそ、「市民が黙っていてくれたほうがいい」というのが本音なのです。
市民の「目」と「声」を恐れている
そもそも、真に信頼される政治家なら、国民が政治に関心を持ち、積極的に関与することを歓迎するはずです。
なぜなら、自らの仕事や政策が、開かれた議論の中で評価されることで、信頼を得る機会にもなるからです。
ところが、一部の議員たちは、そうした市民の「目」と「声」を恐れています。
ネット上での意見や街頭での抗議、署名運動などが広がると、焦ったように「国民の誤解だ」「一部の過激な意見だ」と切り捨てようとする姿勢は、その象徴です。
本当に国民を信用しているなら、たとえ批判であっても、耳を傾けるのが本来の姿ではないでしょうか。
政治参加を妨げるものにNOを突きつけよう
このような構造が続く限り、「私たちが政治に参加しても意味がない」と思わされる空気が社会に広がってしまいます。
実際に、「どうせ何を言っても無駄」「選挙に行っても変わらない」といった言葉を、若い世代を中心に何度も耳にしてきました。
しかし、それこそが一部の政治家の思う壺です。私たちが政治から離れれば離れるほど、彼らの“手の内”で物事が決まっていくのです。
だからこそ、選挙に行くという行動は、彼らへの明確な意思表示です。「私たちは黙っていない」「見ているぞ」と示す一票が、政治の緊張感を取り戻す鍵となります。
信じていない議員には信任を与えない
政治家の本音を見抜くのは簡単ではありません。しかし、国会での態度や発言、メディアへの姿勢、記者会見での説明内容などを見れば、「市民をどう見ているか」は少しずつ透けて見えてきます。
私たちは、国民を“信じていない”政治家に、もうこれ以上権力を預けるべきではありません。
政治とは、国民と政治家の“信頼”に基づく契約のようなものです。その信頼を裏切る者には、次の選挙で“契約終了”の意思を伝えましょう。投票という行動こそ、最も強い言葉です。