砂漠では昼夜の温度差が非常に大きく、日中は摂氏50度近くまで上がる一方、夜には氷点下に達することもあります。この極端な温度変化は、砂漠の環境特性によるものです。
具体的には、
①砂漠の地表が熱を吸収しやすく放射しやすいこと、
②湿度が低く熱を保持しにくいこと、
③大気の影響が少なく地表の熱がすぐに宇宙へ逃げてしまうこと
が主な要因です。
この記事では、それぞれの要因について詳しく解説します。
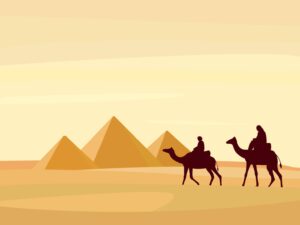
砂漠の極端な気温変化の仕組みとは?
砂漠は、昼夜の気温差が激しいことで知られています。その仕組みを理解するには、まず砂漠の地表の特徴を知る必要があります。
砂漠の地面は主に砂や岩で構成されており、これらの物質は熱を吸収しやすく、蓄えにくい性質を持っています。日中、太陽光が直接地表に降り注ぐと、砂や岩は急速に熱を吸収し、その表面温度は50度以上にも達します。しかし、これらの物質は熱を保持する能力が低いため、日が沈むとすぐに熱を放出してしまいます。その結果、気温が急激に下がるのです。
一方、森林や草原のような環境では、土壌に含まれる水分が熱を蓄え、ゆっくりと放出するため、温度変化が緩やかになります。しかし、砂漠にはほとんど水分がないため、日中に蓄えた熱はすぐに逃げてしまい、夜になると一気に冷え込むのです。
昼は灼熱、夜は極寒──砂漠の温度差を生む理由
砂漠の昼夜の寒暖差が激しい理由のひとつは、湿度の低さです。湿度が低いと空気中の水蒸気が少なくなり、熱を保持する能力が極端に低くなります。
一般に、水蒸気は地表からの熱放射を遮る役割を果たします。湿度の高い地域では、昼間に蓄えられた熱が水蒸気によって保持され、夜になっても気温の低下が緩やかになります。しかし、砂漠では湿度が極端に低いため、この効果がほとんど働きません。その結果、昼間に地表が蓄えた熱は、日が沈むと同時に急速に宇宙へ放出され、気温が急激に下がるのです。
また、砂漠では雲が少なく、日中は強烈な日射が地表に降り注ぐ一方、夜は放射冷却が進みやすいという特徴があります。湿度が低く雲もほとんどないため、昼間の熱が夜にはほぼすべて宇宙へ逃げてしまい、極端な寒暖差が生じるのです。
湿度・地表・大気の影響? 砂漠の寒暖差が激しいワケ
砂漠の昼夜の温度差が大きい理由は、地表や湿度だけでなく、大気の性質にも関係しています。
通常、地表で温められた空気は上昇し、対流によって熱が大気全体に広がります。しかし、砂漠のような乾燥地帯では、この対流が弱いため、熱が地表近くにとどまりやすくなります。日中、砂漠の地表が急速に熱せられると、その熱がほぼ直接的に空気を暖め、地表付近の気温が急激に上昇します。しかし、この熱は地面にとどまりにくく、夜になるとすぐに放射冷却によって奪われてしまいます。
さらに、砂漠では風が強く、夜間に冷たい空気が流れ込むことで気温の低下が一層進みます。都市部などではコンクリートや建物が熱を蓄えるため気温の変動が緩やかですが、砂漠にはそのような熱を保持する要素が少なく、結果的に気温が極端に上下するのです。
まとめ
砂漠の昼夜の温度差が大きい理由は、地表の性質、湿度の低さ、大気の影響という3つの要因が組み合わさっているためです。砂や岩は熱を吸収しやすく放出しやすい特性があり、湿度が低いため熱を保持しにくく、さらに大気の影響で対流による熱の分散が少ないことが、極端な寒暖差を生み出しています。
このような過酷な環境に適応するため、砂漠の生き物たちは昼間に地中に潜ったり、夜に活動したりするなど、独自の生存戦略を持っています。砂漠の厳しい気候を知ることで、地球上のさまざまな環境の特徴や、生き物たちの適応力の素晴らしさを改めて感じることができるでしょう。


