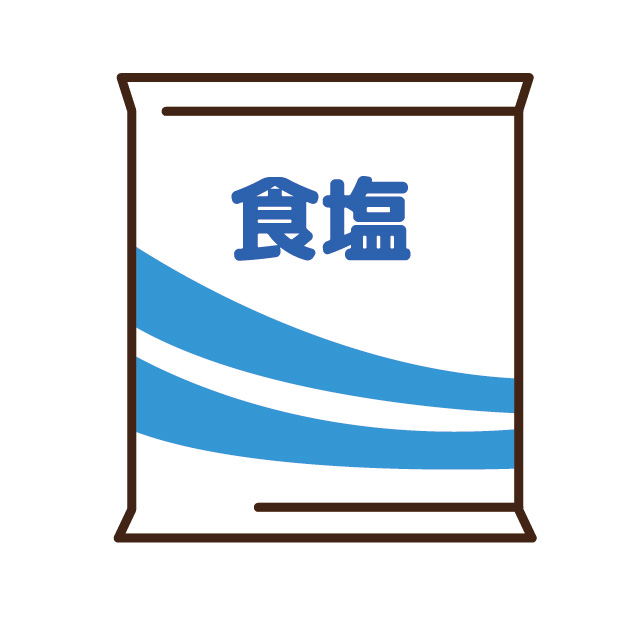現代の健康指導では「減塩」が定番のアドバイスとして語られます。高血圧や心臓病、腎疾患の予防のために、塩を控えましょう――と。
しかし、ここでひとつ大きな疑問が浮かびます。
「どの塩を減らすべきなのか?」
この問いに正しく答えられる医師や栄養士は、残念ながら少数派です。
ほとんどの指導では、精製塩と自然塩の区別がないまま、「塩=悪」として一括りにされてしまっています。
精製塩と自然塩の違いとは?
精製塩:化学的に精製された塩化ナトリウム(NaCl)。ほぼ純粋なNaClで、工業的に大量生産され、ミネラルはほとんど含まれません。味がとがっていて、安価。食品加工や保存料として広く使用されます。
自然塩:天日塩・岩塩・海塩など。マグネシウム、カリウム、カルシウムなどの微量ミネラルを豊富に含み、身体の電解質バランスを整える重要な働きをします。
人間の体液は、海水の成分に近い構成を持っています。ナトリウムだけでなく、ミネラルの複合的なバランスが健康維持に不可欠です。
なぜ精製塩が使われるのか?
それは「安価で大量生産が可能だから」。製薬会社、食品メーカー、外食産業――効率とコスト重視の世界では、自然塩よりも圧倒的に精製塩が都合がいいのです。
そして、その塩が加工食品・レトルト食品・ファストフードの中に溢れ、現代人の身体に負担を与えています。
問題は「塩」そのものではなく、精製された塩だけが過剰に使われていることなのです。
減らすべきは“塩”ではない、“質の悪い塩”だ
自然塩には体の調和を整える力があります。むしろ適切な塩分補給がないと、脱力感・めまい・集中力低下などの不調を引き起こすことさえあります。
現代医療は、症状だけを見て薬で抑えることに慣れすぎています。しかし、身体が求めているのは、薬ではなく、正しいミネラルバランスなのではないでしょうか。