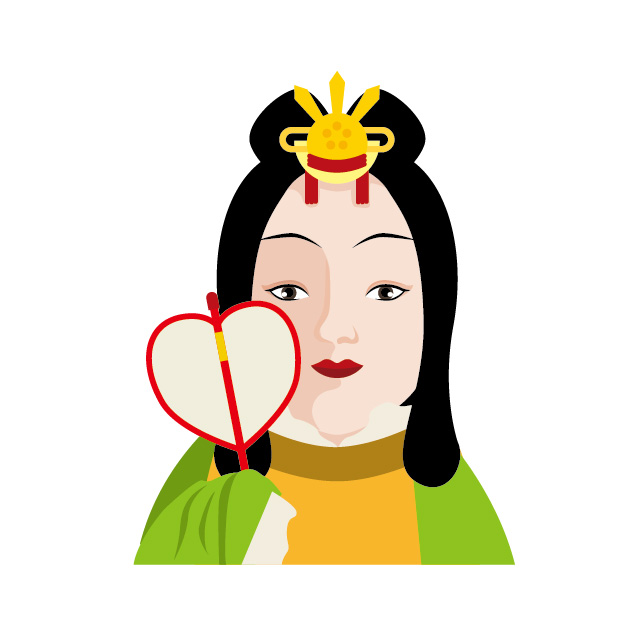日本の歴代天皇の中には、8人10代の女性天皇(女帝)が存在しました。推古天皇から後桜町天皇まで、さまざまな時代に即位しています。
その中で注目すべきは、結婚歴を持つ女帝たちが「夫を失った後」に即位しているという事実です。本記事では、その4人の女性天皇に焦点を当てて、歴史的背景を見ていきます。
推古天皇 ― 日本初の女性天皇
第33代推古天皇は、敏達天皇の皇后でした。敏達が亡くなった後、推古は未亡人となり、後に天皇に即位します。
推古天皇は日本史上初めての女性天皇であり、聖徳太子を摂政として政治を行ったことでも知られます。
夫を失った後、女性が最高権力者として立った最初の例となりました。
皇極天皇/斉明天皇 ― 二度即位した女帝
第35代皇極天皇(のちの第37代斉明天皇)は、舒明天皇の皇后でした。
舒明の死後、彼女が天皇の座につきます。一度は退位しますが、政局の混乱を受けて再び即位し、斉明天皇として国を治めました。
夫を失った後に即位しただけでなく、二度の即位という特異な存在でもあります。
持統天皇 ― 天武天皇の皇后から自ら天皇へ
第41代持統天皇は、天武天皇の皇后でした。天武の死後、その遺志を継ぐかたちで即位します。
飛鳥時代から奈良時代にかけての律令国家の整備を進め、「大宝律令」の施行や藤原京遷都などを主導しました。
持統天皇は、夫を失った後に権力を継承し、自ら国家の舵を取った代表的な女性天皇です。
元明天皇 ― 草壁皇子の早逝を受けて
第43代元明天皇は、草壁皇子(天武天皇と持統天皇の子)の妃でした。ところが、草壁皇子は即位する前に早逝してしまいます。
夫を失った元明は、息子・文武天皇が若くして亡くなった後、自ら即位して皇統を安定させました。
母として、また未亡人としての立場から即位したのです。
女性天皇の特徴 ― 夫の死後に即位する
以上の4人に共通するのは、夫が生きている間に即位した例は一つもないという点です。いずれも夫を亡くした後、未亡人として皇位を継いでいます。
これは、女帝が「皇統の中継ぎ」としての役割を担ったことを示しています。もし夫とともに在位すれば、夫(外戚)に権力が集中する懸念がありました。
そのため、女性天皇は独立した存在として、夫亡き後に政権を安定させる役目を担ったのです。
終生独身の女性天皇
一方、元正・孝謙/称徳・明正・後桜町といった女性天皇は、そもそも結婚せずに生涯を終えています。
こうした女帝もまた、権力のバランスを保つための「中継ぎ役」としての性格を強く持っていました。
まとめ
日本の歴代女性天皇の中で結婚歴のある4人は、すべて夫を亡くした後に即位しました。女帝は、夫の皇統や子どもの皇位継承を守るための「橋渡し役」として登場したのです。
未亡人として即位した女帝の存在は、日本の皇室史において特異でありながらも、皇統の安定を守るために不可欠な存在だったといえるでしょう。