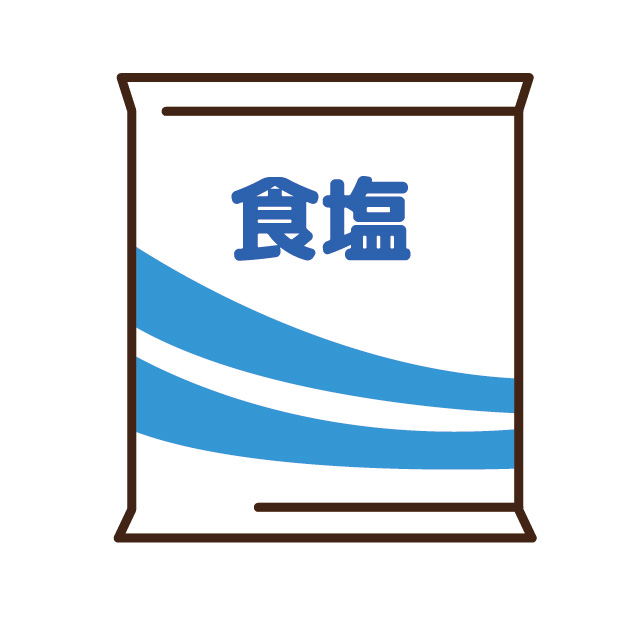私たちは健康のために「塩分は控えめに」とよく言われます。実際、WHO(世界保健機関)は、一日の塩分摂取量を5グラム未満にすることを推奨しています。
しかし最近、塩分を減らしすぎると、かえって健康に悪影響が出るという研究結果がいくつも報告され、専門家の間でも議論が起きています。
今回は、そうした最新の研究を紹介しながら、「塩分との付き合い方」について考えてみましょう。
WHOはなぜ「塩を減らせ」と言うのか?
WHOが塩分制限を勧める理由は明確です。塩に含まれるナトリウムが血圧を上げることは広く知られており、高血圧は脳卒中や心疾患の最大のリスク要因の一つです。
加工食品や外食に含まれる隠れた塩分量も問題視されており、WHOは「成人は一日5グラム未満(ナトリウム換算で約2g未満)」を目安とするように呼びかけています。
ところが、一部の研究は「少なすぎる塩分はかえって危ない」と警告。
一方で、塩分を極端に制限した人のほうが、死亡率が高くなるという研究も複数存在します。
その代表的なものが、PURE研究(Prospective Urban Rural Epidemiology)です。これはカナダ・マクマスター大学を中心に行われた、世界的な大規模調査です。
この研究では、塩分摂取量と死亡率・心疾患リスクとの関係を調査した結果、
一日10〜15グラム程度の塩分を摂っている人のほうが、最も心血管系の死亡率が低い
という「U字型」の関係が見られたのです。つまり、「塩が多すぎるのも悪いが、少なすぎるのも良くない」という結果です。
なぜ塩分が少なすぎると危険なのか?
ナトリウムは単なる“味つけ”ではなく、体液のバランスや神経伝達、筋肉の働きに欠かせないミネラルです。
塩分を制限しすぎると、次のような問題が起きる可能性があります。
低ナトリウム血症によるだるさや頭痛
ホルモンバランスの乱れ(アルドステロン・レニン系)
食欲低下や代謝不全
心疾患リスクの上昇(逆説的ですが)
特に健康な人が無理に塩分制限をすると、かえって体調を崩すケースもあるのです。
では、どのくらいが「適量」なのか?
ここが難しいところですが、研究結果を総合すると以下のような目安が浮かび上がります。
高血圧・心疾患リスクのある人:塩分は控えめ(5~6g/日未満)が望ましい
健康な成人:過剰な制限は不要。10g前後(ナトリウム4g程度)でもリスクは低い
運動量の多い人・汗をかきやすい人:ナトリウムを意識的に補給すべき場合も
また、「精製塩」ではなく、「自然塩」や「ミネラルを含む塩」を選ぶことも重要です。塩分の質によって、体への影響は大きく変わってきます。
結論:減塩は「目的」と「体質」に応じて柔軟に
塩分を完全に悪者にする時代は、終わりつつあるのかもしれません。
大切なのは、「誰にとっても5g未満」という一律の基準ではなく、その人の体質・生活習慣・疾患リスクに応じてバランスを取ることです。
極端な減塩がかえって健康を害することもある、という事実を私たちはもっと知っておくべきではないでしょうか。