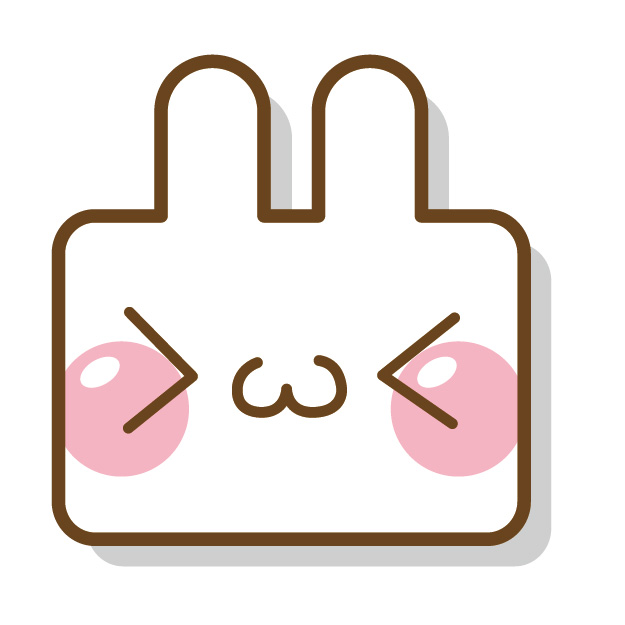大地震のとき、津波の警報が鳴っても避難しなかった人がいた。感染症が拡大しても「自分はかからない」と信じて外出を続けた人がいた。
こうした行動の背景にあるのが正常性バイアス(Normalcy Bias)です。
人は異常な事態に直面すると、無意識のうちに「これはいつもの延長だ」「たいしたことはない」と考えてしまう。この心理的メカニズムこそが、時に命を左右するほどの影響を及ぼします。
正常性バイアスとは何か
正常性バイアスとは、非常事態を前にしても「まだ大丈夫」「そんなはずはない」と現実を過小評価してしまう心の働きです。
人間の脳は、急激な変化や不安をもたらす情報に対して自己防衛的に「認知の平衡」を保とうとします。
つまり、危険を受け入れるよりも「いつも通り」と思い込む方が心理的に楽なのです。
このため、災害・事故・戦争・経済危機などの初期段階で、人々が避難や行動を遅らせてしまうのは珍しくありません。
歴史が示す「気づかなかった悲劇」
正常性バイアスは、歴史上何度も人命を奪ってきました。
東日本大震災(2011年)
津波警報が出たにもかかわらず、「この町は大丈夫」「前回も来なかった」と避難を遅らせた人が多く、結果的に多くの犠牲を生みました。
太平洋戦争前夜
ヨーロッパで戦争が迫る中でも、「まさか本当に始まるはずがない」という空気が蔓延し、対応が遅れた国がありました。
経済バブルの崩壊
「景気は永遠に続く」「今が普通だ」という楽観が、バブル崩壊の被害を拡大させました。
これらはすべて、人間の「異常を正常とみなしたい心理」が生んだ結果です。
現代社会にも潜むバイアス
このバイアスは災害時だけでなく、現代社会のあらゆる場面に潜んでいます。
政治・行政の無策
「この国は安定している」「危機は起こらない」という思い込みが制度改革を遅らせます。
企業経営
「今まで成功してきたから今回も大丈夫」という慢心が、時代の変化に取り残される原因になります。
個人の生活
健康診断の結果を軽視したり、異変を感じても「気のせい」と片づけたりする。これも正常性バイアスの一種です。
正常性バイアスと情報麻痺
非常時には膨大な情報が一気に流れ込みます。SNSやニュースの速報があふれ、何を信じていいかわからなくなると、人は「何もしない」ことを選びます。
実はこの「判断停止」こそが、正常性バイアスによる情報麻痺(information paralysis)です。
「何か行動を起こすリスク」よりも「何もしない安心」を選んでしまうのです。
対策―想像力と訓練が命を救う
正常性バイアスを克服する鍵は、「あり得ないことを想定しておくこと」です。
危機を“想像”する訓練を持つ
「この地域で地震が起きたら」「電気が止まったら」と、仮定のシミュレーションをしておくと、脳が“異常”を受け入れやすくなります。
小さな異変を軽視しない
「いつもと違う」という違和感を感じたら、それを無視せず確認する。日常の中で感度を保つことが重要です。
周囲と声をかけ合う
人は集団の中で行動を合わせがちです。「みんな逃げないから自分も」ではなく、「自分が動けば周りも動く」意識を持つこと。
情報の複数確認
テレビ・ラジオ・ネット・自治体アプリなど、複数の情報源を使って事実をクロスチェックすることで、思い込みを減らせます。
まとめ
正常性バイアスは、私たちが安心を求めるがゆえに生まれる「心の防衛反応」です。しかし、非常時にはそれが命取りになります。
「異常を正常と思い込む」ことが最大の危険であると知るだけでも、行動の早さが変わります。
平常心と油断は違います。真の冷静さとは、「最悪を想定した上で、最善を尽くす姿勢」です。
日常の安心感の裏側に潜む“正常性バイアス”を意識し、いざというとき自分と周囲を守れる判断力を磨いていきたいものです。