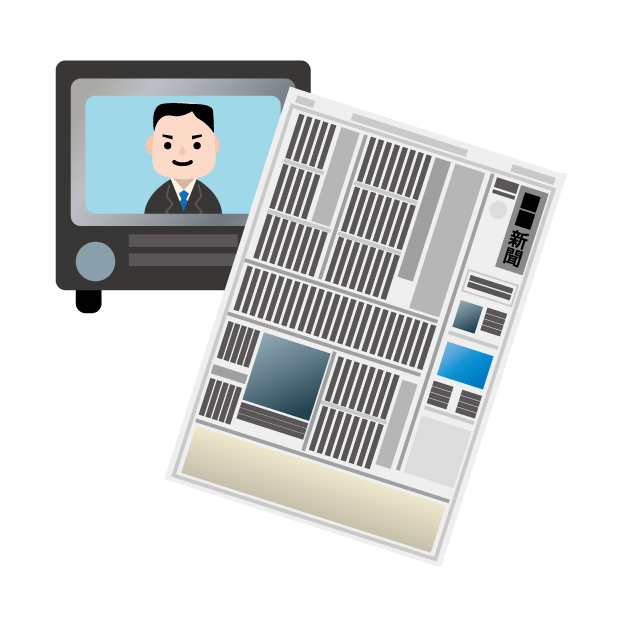ニュースを見ていて、「この報道はなぜこういう言い方をするのだろう?」と感じたことはありませんか?
同じ出来事を伝えているのに、あるメディアでは肯定的に、別のメディアでは否定的に聞こえる。
実はそこにはフレーミング効果(framing effect)という心理的な仕組みが関わっています。
フレーミング効果とは
フレームとは「枠組み」のことです。フレーミング効果とは、事実そのものは同じでも、どの枠組みで表現するかによって人の受け止め方が変わるという心理現象です。
心理学の有名な実験では、「ある手術の成功率が90%」と聞いた場合と、「失敗率が10%」と聞いた場合とで、人々の受け止め方が大きく変わることが示されています。
数値的には同じ意味でも、「成功」と「失敗」という枠組みの違いが感情を動かしてしまうのです。
報道におけるフレーミングの実例
フレーミング効果はニュースでも日常的に使われています。
経済政策
「増税で財政健全化」と伝えれば前向きに聞こえますが、「増税で国民負担増」と報じれば否定的な印象になります。どちらも事実ですが、印象は正反対です。
失業率
「失業率が5%」と言うのと、「就業率が95%」と言うのでは、聞き手の受け止め方は異なります。前者は不安を、後者は安心感を与えます。
災害報道
「死者100人」と表現するのと、「生存者は多数」と表現するのとでは、同じ事実でも人々の感情の動きが大きく変わります。
このように、ニュースの言葉選び一つで、国民の心理や世論が操作されてしまうのです。
政治的利用の典型
政治家や政府は、この効果を意図的に利用することがあります。
例えば、軍事行動を「侵略」と呼ぶか「自衛」と呼ぶかで、国民の支持率は大きく変わります。
また、原発事故後に「安全基準を厳格化した」と言えば安心感が広がりますが、「従来の基準では不十分だった」と報じれば不安が強調されます。
言葉の選び方=フレーミングは、単なる言い換えではなく、国民の行動や投票行動を左右する重要な武器になるのです。
私たちが惑わされる理由
なぜ人はフレーミング効果に弱いのでしょうか。理由の一つは、人間の思考が合理性より感情に大きく左右されるからです。
ポジティブな枠組みで提示されると安心し、ネガティブな枠組みで示されると恐怖や怒りが先に立ちます。
そのため、同じ数値や事実でも、感情の方向性が印象を決定してしまうのです。
フレーミング効果に対抗する方法
フレーミング効果は巧妙ですが、意識するだけでも対抗することができます。
言い換えて考える
「成功率90%」と聞いたら「失敗率10%」と自分で言い換える。逆もまた然り。両面から見る習慣を持つと冷静に判断できます。
複数メディアを比較する
同じ出来事をどう枠づけて報じているかを比較すると、どこに偏りがあるのかが見えてきます。
事実と感情を切り分ける
数字や事実をまず確認し、それにどういう感情を抱かされているのかを自覚することが大切です。
まとめ
フレーミング効果とは、メディアが「どの枠組みで事実を見せるか」によって、私たちの印象や判断を変えてしまう力です。
報道の中で使われる言葉は単なる表現ではなく、世論を動かす強力な道具なのです。
この効果を理解し、「別の言い方ならどう聞こえるか?」と考える癖を持つこと。それが偏向報道に惑わされず、自分の頭で考えるための重要なリテラシーになります。