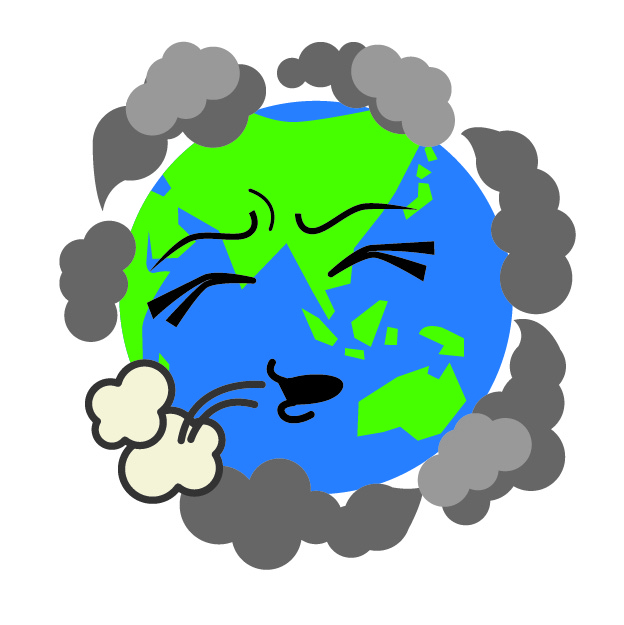「アメリカではもう規制されているんでしょ?」
「ヨーロッパでは禁止されたってニュースで見た」
「でも日本は……?」
そう、世界がPFASに対して“待った”をかけ始めている今、日本だけが取り残されているように見えるのです。
なぜ日本では規制が進まないのでしょうか?
そこには単なる無関心ではない、企業と行政、そして法制度の構造的な問題が横たわっています。
世界では「PFAS=有害」としての扱いが明確に
ここ10年ほどの間に、欧米を中心とする国々では、PFASへの対応が急激に進みました。
まず、アメリカでは2024年、環境保護庁(EPA)がPFOSやPFOAを“有害物質”として法的に指定しました。
これは「スーパーファンド法」と呼ばれる法律の下で、汚染が発覚した場合、排出企業に巨額の賠償と浄化義務を課すものです。
また、飲料水中のPFAS基準値も大幅に引き下げられ、1リットルあたり0.004ナノグラムという超低濃度が上限とされました。
ヨーロッパでは、EUが2025年にもPFAS全体を包括的に規制する方向で法案を審議中です。
特定の物質だけでなく、「フッ素炭素鎖を含む化合物全体」に対して原則禁止という、世界で最も厳しいレベルの規制となる予定です。
つまり、世界ではすでに「PFASは危険であり、早急に減らすべきもの」だという共通認識ができつつあるのです。
日本では「暫定目標値」どまり
それに対して、日本の現状はどうでしょうか?
厚生労働省と環境省は、2020年に「PFOSとPFOAの合計で、50ナノグラム/リットル以下が望ましい」という“暫定目標値”を設定しました。
しかしこれは、あくまで行政上の“目安”であり、法律上の規制基準ではありません。
つまり、水道水から基準値以上のPFASが検出されたとしても、ただちに違法とはならず、罰則もありません。
しかも、アメリカの0.004ナノグラムと比べれば、日本の基準値は実に1万倍以上も緩いことになります。
「日本の水道水は世界一安全」と思い込んでいる人が多い中で、本当に守られるべきは誰なのかという問いが、いま静かに突きつけられています。
なぜ日本では規制が進まないのか?
この問題を語るうえで避けて通れないのが、日本の“産業優先型行政”の構造です。
PFASを長年製造・販売してきた企業として、日本では以下のような企業が関与してきました:
ダイキン工業
AGC(旧・旭硝子)
三井・デュポンフロロケミカル
これらの企業は、フッ素系製品を「社会に欠かせない高機能素材」として正当化しながら、「新PFAS(短鎖型)や代替品への移行を進めている」と主張しています。
しかし、その“代替品”がどれほど安全なのか、十分なデータが公開されているとは言い難いのが現状です。
にもかかわらず、これらの企業の意見が政府の規制判断に大きく影響を与えていると見られています。
つまり、健康よりも産業保護が優先される構造が、規制の遅れの背景にあるのです。
規制を求める声は現場から上がっている
一方で、汚染が実際に確認された地域では、住民や医師、市民団体が声を上げ始めています。
沖縄県:米軍基地周辺の地下水からPFASが検出され、地元住民が調査と情報公開を求める運動を展開。
東京都多摩地域:高濃度のPFASが地下水から検出され、市民団体が都議会に改善を求める請願を提出。
大阪府摂津市・高槻市:淀川流域のPFAS汚染に対し、周辺住民が企業名の公表と対策の明示を要求。
こうした「現場の声」は徐々に行政を動かし始めていますが、制度的な“壁”が厚いのもまた事実です。
法改正、企業への責任追及、被害者の救済制度など、まだまだ課題は山積しています。
私たちにできることは?
「日本は遅れている」と言って終わりにしてしまっては、何も変わりません。
だからこそ、以下のような“小さな行動”が、大きな変化につながっていくのです。
地元自治体の水質調査結果を確認する
もし情報が公開されていなければ、住民として問い合わせや請願を行うことができます。
企業に対して説明責任を求める声を届ける
株主としての立場から、消費者としての立場から、「安全な製品を選びたい」という意思表示を。
選挙で環境政策に取り組む候補を応援する
健康と環境を守る政策を掲げる議員を後押しすることで、法律や制度が変わっていきます。
情報をシェアし、周囲に伝える
「そんなこと知らなかった」という人が、気づくきっかけになるだけで、十分な意味があります。
世界基準の安心を日本にも
PFASの問題は、決して“一部の地域だけの特殊な話”ではありません。
今や全国的な汚染リスクがあるにもかかわらず、国の対応は遅れたまま。
一方で、世界ではすでに「予防原則」に基づいた行動が始まっています。
私たちの健康を守るのは、私たち自身。世界基準の安心と未来を、日本にも。
そのためには、「無関心でいない」こと、そして「声を上げること」からすべてが始まります。