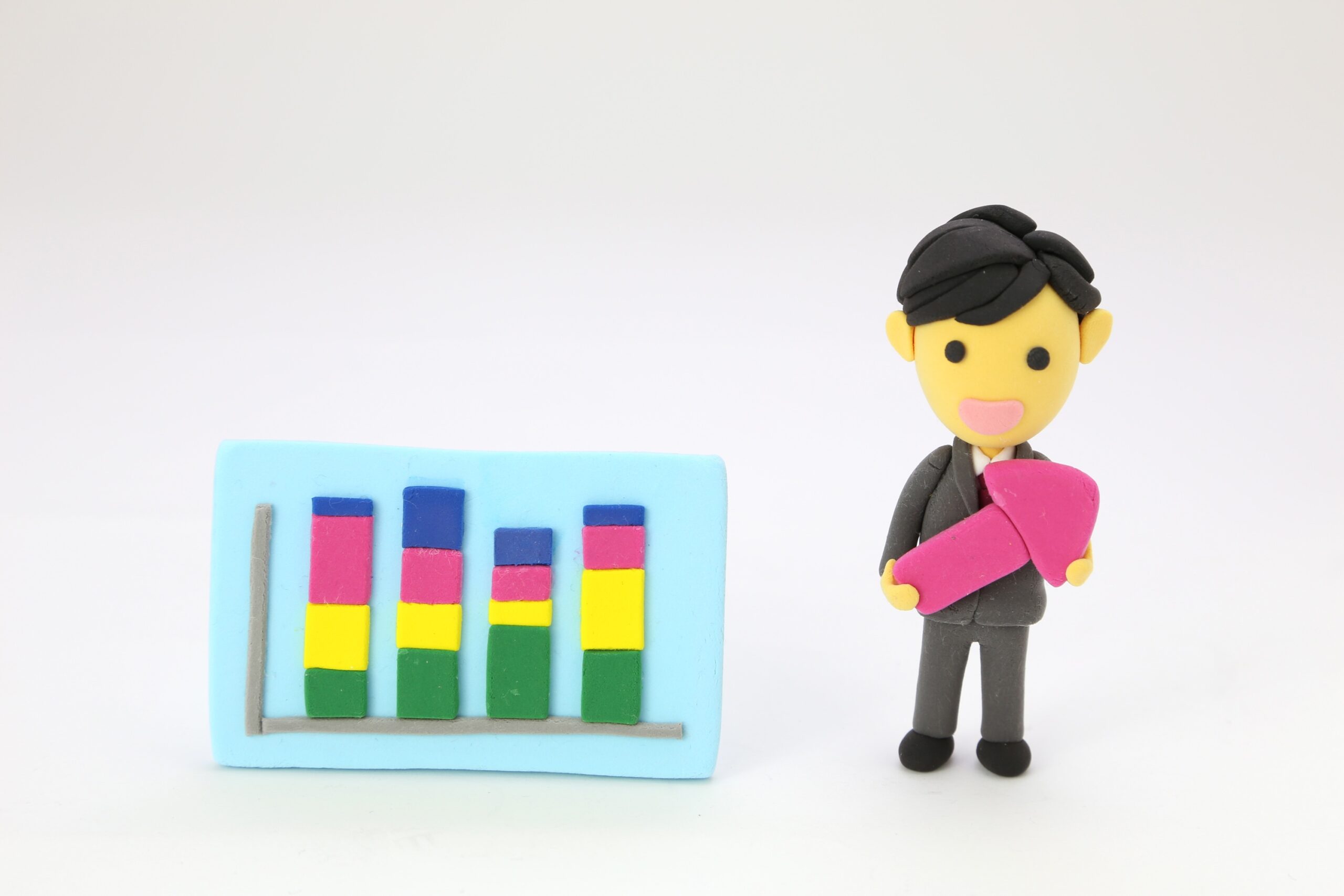「税」は本当に苦しいだけのものなのか?
多くの日本人にとって、「税金」は苦痛の象徴のような存在です。
「どんどん取られるばかり」
「何に使われているのか分からない」
「払っても生活が良くならない」
でも、世界を見渡せば、「税金を払うことで安心が得られる」「納税は信頼の証」と感じられる国も存在します。
つまり、制度設計しだいで“優しい税制”は実現可能なのです。
今回は、いくつかの国の実例を通して、公正な税制がどのように市民生活を支えているのかを見ていきましょう。
スウェーデン:高福祉・高負担でも納得される税制
スウェーデンの消費税(付加価値税)は25%と高水準。しかし、国民の不満は比較的少ないことで知られています。
✔ポイントは「使い道の明確さ」と「負担の公平さ」
子どもの教育費は大学まで基本無料
医療費や介護はほぼ無償、自己負担上限あり
育児休暇は最大480日、給与の約8割が支給される
高所得者には高い所得税(最高55%)
つまり、「負担は大きいが、見返りも大きい」
そして、「富裕層にもきちんと課税されている」ことが信頼の基盤になっています。
🗨国民は“税を払うことで社会とつながっている”と実感している。
フランス:富への課税で格差を是正する仕組み
フランスは「連帯」が政治文化の根底にあり、累進課税と富裕層への課税に積極的です。
所得税は最大で45%
社会保険料は高いが、手厚い医療・住宅支援あり
富裕層に対しては「富の連帯税」(旧・ISF)を導入していた時期もある
また、非課税最低所得の範囲が広く、低所得者には実質的に課税されない構造です。
🗨社会的弱者を守るという合意が、税制にも明確に反映されている。
ドイツ:中間層重視のバランス型税制
ドイツの税制は、「中間層を豊かに保つこと」が経済政策の軸です。
所得税は累進で、可処分所得が大きく残る仕組み
消費税(付加価値税)は19%、生活必需品は軽減税率7%
教育や医療は充実、貧困層には手当と住宅支援がある
中小企業支援が厚く、雇用の安定に寄与している
また、財政黒字化を重視しつつも“削る福祉”には慎重です。
🗨税金の使い道が、社会の安定と未来の投資になっている。
日本との違いはどこにあるのか?

なぜ海外では「税」が受け入れられるのか?
“取られる”のではなく“支え合い”という認識
政府への信頼と説明責任の文化
社会全体が「連帯」を価値として共有している
制度設計に市民の声が反映されやすい仕組み
一方、日本では「自己責任」と「見えない使途」が組み合わさり、税に対して“重いだけで報われない”という印象が固定化されています。