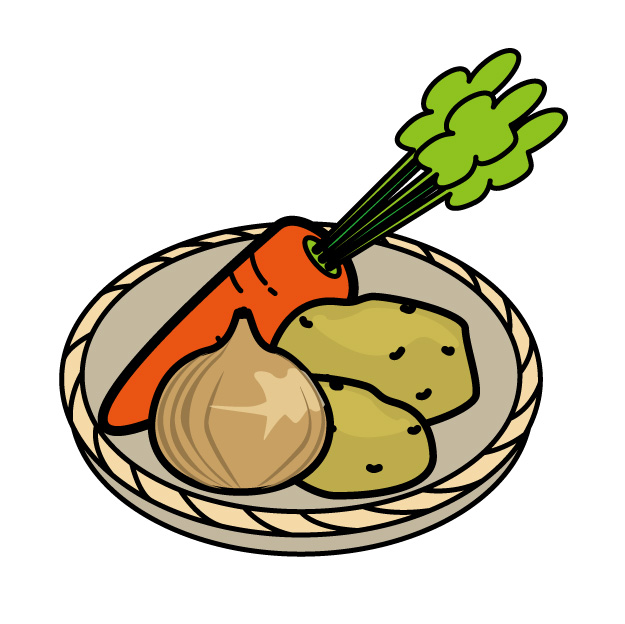「ベジタリアンが増えている」という話題が世界で注目される中で、ふとこんな疑問を抱く人もいるかもしれません。
「日本人って、もともと肉をあまり食べない民族だったのでは?」
実はそれ、半分正解です。そして半分は時代の変化によって変わってきた側面もあります。
本記事では、日本における菜食文化の歴史と現代の食生活の変遷をたどりながら、「日本人と菜食」の関係をあらためて見つめてみたいと思います。
🏯 古代〜江戸時代:仏教と共に育まれた「菜食の国」
◉ 肉食禁止令は天皇から始まった
日本で本格的な肉食制限が始まったのは、675年。天武天皇が出した有名な「肉食禁止令」によって、牛・馬・犬・猿・鶏の肉を食べることが禁じられました。
これは仏教の教えに基づくものであり、殺生を避けるという精神が日本全体の食文化に深く影響を与えました。
◉ 魚はOK?ペスカタリアン的な文化
とはいえ、魚は「四足動物ではない」として例外とされることが多く、日本では魚と野菜を中心とした、いわば「和風ペスカタリアン」ともいえる食生活が長く続きました。
特に江戸時代の庶民の食事は、「一汁一菜」あるいは「一汁三菜」といった質素なもので、主食は米、副食は豆腐や野菜、漬物、少量の魚などでした。
🍖 明治時代以降:文明開化とともに肉食解禁へ
◉ 明治天皇の「牛鍋」が象徴的な転機に
1872年、明治天皇が「牛鍋(すき焼き)」を食べたという逸話が大きなニュースとなり、それまでの肉食忌避が大きく転換します。
政府は国民の体格向上や欧米化の象徴として「肉食は文明の証」と位置づけ、西洋料理や肉食文化が急速に広がりました。
その後の戦後復興と経済成長にともない、肉・乳製品・卵を中心とする食生活が日常化していきます。
🥗 現代日本と「ベジタリアン」という言葉
◉ 食生活は欧米化、でも菜食文化の再評価も
現代の日本では、ステーキ・ハンバーグ・唐揚げなどが食卓の定番となり、肉の消費量は世界的にも高い水準に達しています。
しかし一方で、健康志向や環境意識の高まりとともに、和食に根ざした菜食文化を見直そうとする動きも広がっています。
◉ ベジタリアン・ヴィーガン人口の現状(推定)
ヴィーガン:約0.4%
ベジタリアン:約2.1%
欧米に比べるとまだ少ないものの、「週に数日は肉を控える」「プラントベースの食事を意識する」といった柔軟な菜食志向(フレキシタリアン)が徐々に増加しています。
✅ まとめ:日本の伝統に見る「未来の食」
日本にはもともと、「動物性食品を控え、植物中心に生きる」という精神が、仏教や和食文化の中に深く根付いていました。
それは単なる健康志向にとどまらず、自然への畏敬や、命を大切にするという倫理観にもとづいた暮らし方だったのです。
日本人の菜食文化は、サステナブルなライフスタイルのヒントにあふれています。