 情報判断力
情報判断力 後知恵バイアス―「最初から分かっていた」という思い込みの罠
事件や災害、選挙や経済のニュースを見たあとで、「やっぱりこうなると思っていた」「最初から分かっていた」と感じたことはありませんか?しかし実際には、その“予感”はほとんどの場合、後から作られた記憶です。この心理現象を後知恵バイアス(Hinds...
 情報判断力
情報判断力  情報判断力
情報判断力  情報判断力
情報判断力  情報判断力
情報判断力 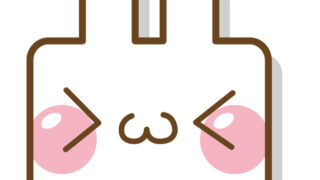 情報判断力
情報判断力  情報判断力
情報判断力  情報判断力
情報判断力  情報判断力
情報判断力  情報判断力
情報判断力  情報判断力
情報判断力