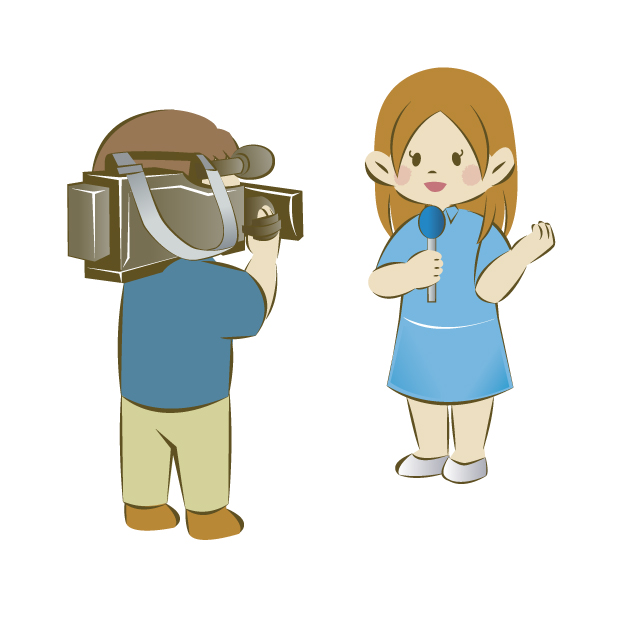ニュースは「事実を伝えるもの」と思いがちですが、実際には言葉の選び方によって印象が大きく左右されます。見出し一つ、形容詞一つが、視聴者や読者の感情を操作するのです。
ここでは、実例を交えながら「言葉づかいを疑う」習慣を身につける方法を考えてみましょう。
ニュースの中の言葉のトリック
まずはよく見かける表現です。
「批判殺到」:SNSの数件の投稿を「殺到」と表現することで、大きな社会現象に見せかける。
「波紋を広げている」:実際には一部の人だけの反応でも、全国的な影響があるように装える。
「〜の可能性」:根拠が薄くてもニュースに仕立てられる便利な言葉。
「関係者によると」:誰の発言か分からないまま、裏付けのない情報を「事実らしく」伝えられる。
「疑惑」:立証されていなくても、疑いを植え付けることができる。
これらの言葉は事実を伝えるのではなく、受け手に「どう感じさせたいか」に基づいて選ばれていることが多いのです。
情報を正しく読み取る4つの方法
事実と意見を分ける
「〜と批判されている」という表現は事実ではなく評価です。誰が言っているのか、実際の発言や数字を確認しましょう。
一次情報にあたる
政府統計や公式発表、元の演説や議事録に戻ると、報道の切り取り方が見えてきます。
表現を数字や主体に置き換える
「殺到」→「何件?」、「波紋」→「誰が?」と具体的に考えることで、誇張表現を冷静に捉えられます。
別のメディアと比較する
同じ出来事を複数の新聞やテレビ局で見比べると、どの言葉を選び、どの視点を省いたのかが鮮明になります。
まとめ
ニュースに登場する言葉をそのまま受け入れず、疑いの目で読み解く習慣を持つこと。それが「印象操作に惑わされないリテラシー」につながります。メディアの言葉の裏にある意図を見抜けるようになると、ニュースをより立体的に理解できるでしょう。