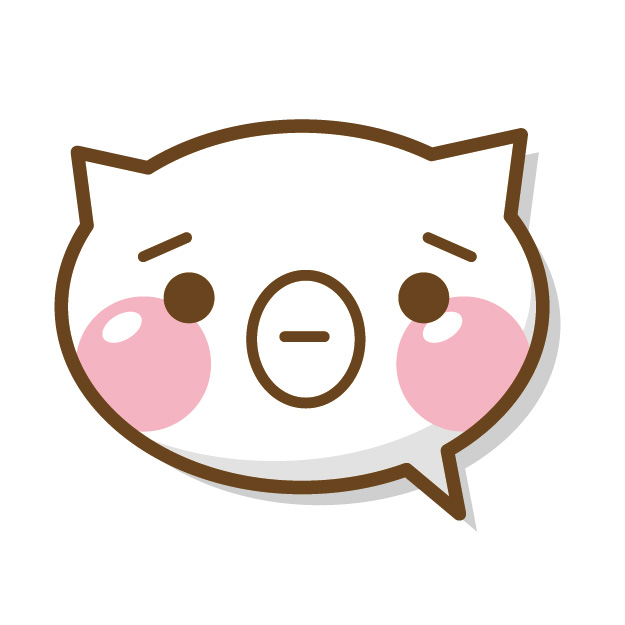他国の人々、別の政党の支持者、あるいは他の職業の人たち。
自分とは違う集団を思い浮かべるとき、「彼らは皆、似たような考えをしている」と感じたことはありませんか?
そのように他の集団の人々を「一様で個性がない」と感じてしまう心理を、アウトグループ同質性バイアス(Out-group Homogeneity Bias)と呼びます。
これは、前回扱った「内集団バイアス」と対になる概念であり、現代社会の偏見・差別・誤情報拡散の根底に潜む、人間の深い心理構造でもあります。
アウトグループ同質性バイアスとは
アウトグループ同質性バイアスとは、自分が属していない集団(外集団)のメンバーを、実際よりも“みな同じ”だと感じる傾向のことです。
逆に、自分の所属する集団(内集団)については、「多様で個性的」「一人ひとりが違う」と感じやすいのが特徴です。
つまり私たちは、
内集団 → 「個性豊かな仲間たち」
外集団 → 「同じような人たち」
と無意識に分けて見てしまうのです。
実験による証拠
1970年代、心理学者ジョン・レインヴィルとスティーヴン・ジョーンズは、大学生を対象に実験を行いました。
学生たちは、同じ大学内の他の学部の学生たちを「グループ外」として評価しました。
その結果、学生たちは、自分の学部の人々については「個性があり多様」と答えたのに対し、他学部の学生たちについては「似たようなタイプが多い」と回答したのです。
これはつまり、人は自分が“中にいる”集団を細かく見分け、“外にいる”集団を大ざっぱにひとまとめにしてしまうことを意味します。
日常に潜むアウトグループ同質性バイアス
国際関係
「外国人はみんな〇〇だ」「あの国の人は全員こうだ」と決めつけてしまう。
政治・思想の対立
「保守派はみんな古い」「リベラルは全員偽善的」といったレッテル貼り。
職業・業界の偏見
「公務員は怠け者」「営業職は口がうまいだけ」など、職業集団に対するステレオタイプ。
学校や組織内の派閥
他のクラス、他部署、他チームの人々を一様に敵視する。
このような思い込みは、事実の理解を妨げ、人間関係の分断を深めます。
なぜ「外の人」は一様に見えるのか
情報の少なさ
外集団に関しては直接接する機会が少なく、断片的な情報だけで全体を判断してしまう。
認知の効率化(脳の省エネ)
人間の脳は複雑な世界を単純化して理解しようとするため、「同じグループ=同じ性質」として処理する。
自己防衛の仕組み
自分の集団を守るために、「外の集団は理解不能な他者」として心理的に距離を置く。
メディアの影響
ニュースやSNSは“分かりやすい構図”を作るため、外集団を「一枚岩」として描きがち。
内集団バイアスとの相互作用
アウトグループ同質性バイアスは、内集団バイアスとセットで機能します。
内集団バイアス → 「仲間を好意的に評価」
アウトグループ同質性バイアス → 「外の人たちはみんな同じで劣っている」
この2つが組み合わさると、偏見・差別・対立が強化され、「分断社会」の心理的基盤が出来上がります。
たとえば政治対立では、「相手陣営はみんな極端だ」と思い込む。この心理が、冷静な議論を不可能にしているのです。
アウトグループ同質性バイアスの社会的影響
偏見・差別の固定化
外集団を“ひとまとめ”にすることで根拠のないステレオタイプが形成される。
対話の断絶
「彼らとは分かり合えない」という思い込みが相互理解を阻む。
メディアによる分断の助長
報道やSNSが“対立構造”を煽ると、ますます他者を同質的に見てしまう。
組織や社会の硬直化
他部門・他国・他宗派の視点が排除され、創造性や協働の機会が失われる。
アウトグループ同質性バイアスを克服するための方法
個人としての多様性を認識する
「Aのグループの人=Aな性格」と決めつけず、一人ひとりを個として見る。
直接的な交流を増やす
“外集団”の人々と会話することで固定観念が崩れていく。
メディアの構図を疑う
「〇〇派」「××国」などのひとまとめ表現には、意図的な単純化が潜んでいる。
自分も“誰かの外集団”であると自覚する
他者を一様に見ているとき、同時に自分も同じように見られている。その視点に立つことで、謙虚さと共感が生まれる。
まとめ
アウトグループ同質性バイアスとは、自分が属していない集団の人々を、実際よりも“同質”に感じる心理的傾向です。
それは脳の省エネ構造と防衛本能から生じる自然な反応ですが、放置すれば偏見・差別・分断を助長します。
人間社会を成熟させるとは、「違いを理解する」ことではなく、「違いを恐れない」こと。
世界を単純化せず、個人の顔を見ようとする――その一歩が、偏見なき社会への最も確かな道です。